| 4コママンガ<ハムとラン> とキャラのページ (c)Shimamura,T |
 |
 |
 |
hardy@max.hi-ho.ne.jp |
年末のような気がしない、という人も中にはいることでしょう。特に新規の開発を担当していて、
思ってもみなかった課題が噴出して、なかなかメドがつかず、日程は遅れに遅れ、
自分がコミットした計画は死守しなければならない、とハッパをかけられているような、そんな技術者は、
年末だからキリがつく、とか、正月だから課題が減るということもなく、
やりかけのシミュレーションや結果の出ていない実験などを残しながら、いったいどうすれば
うまくいくんだ、と夜も眠れず、世間が休みだから仕方ない、
と、泣く泣く休みに突入している人も多いでしょう。
そして、日ごろ忙しさにかまけて読むことのできない論文やハンドブックを、カバンに詰めて持ち帰り、
しかし、休みに入ったとたん、やっぱりのんびりしてしまい、一回もカバンを開けることもなく、
毎日飲みまくったアルコールも抜けないまま、休み明けに会社に行ってみると、
あれ、休み前に、俺、何やってたんだっけ、やりかけていたことは
たくさんあるはずだけど、何だったっけ、てなもんで、2日間もぼけっと過ごすとまた三連休、
スキーにスノボに仲間と遊んで夢中になっているうちに時間はあっという間にたち、
、一月は末になるまでエンジンがかからない人もいるのではないでしょうか。
十数年前、私がまだ、若造だったころ(いや、今も若造ですけどね)、怖かったチームリーダーは
年末の休み前に、眉根に皺をよせて重々しく言ったものです。
「休み明けにやらないといかんことを書き出して、机の上に貼っておけ」
小学生じゃないんだから、とそのときは思ったものですが、そういう立場になってみると
言いたくなるもので、若手のホープT君に冗談めかして言ってしまいました。
「大丈夫です、ノートにしっかりと箇条書きにしてあります。」
ふむん、想定外の言葉。最近の若いもんはなかなかやるもんだね。オンとオフの切り替えが上手い。
今年流行った言葉といえば、この言葉でしょうが、
どうにも聞く人には少し不快感を与えるように思います。
もともと、プロジェクトマネジメントをやっていると、リスクマネジメントはとても大事で
起こるであろういろんなことを想定して、その影響や頻度を評価し、
こうなったらああする、ああなったらこうする、という具合に適切な処置をあらかじめ考えておき、
何が起こっても想定の範囲内にしておくことが求められます。
プロジェクトマネジメントは大規模なソフトウエア開発でよく適用される方法なので、
IT業界の堀江社長が「想定の範囲内」と口にすることは別に何の不思議もなく、実際にそこまで
考えて手を打っている可能性が高いのです。
ただのゲームと違って、ビジネスは「大勝」から「大負け」までの間に、
「勝ち」、「少し勝ち」、「だいたい勝ち」、「見方によっては勝ちとも言える」
「勝ちと言えなくもない」、「勝ったと日記には書いておこう」、などと
いろいろな状態があります。しかも、ルールは一定ではありません。抜け道もたくさんあります。
そして、必ずしも大勝する必要もなく、どんな場合でも「ちょっと勝ち」くらいになっていれば、
OKなのです。
普通の人はそこまで考えませんから、ゲームの後にいろいろ解説されて、得意顔で「想定の範囲内だ」と
言われても、
「お前のその小さな頭でそこまで考えてやってたのか?うまくズルして後から理由つけてるだけなんちゃうの。」
とどうしても感じてしまうのです。
これが上で述べたなんとなく感じる不快感なのでしょう。
違っていて、ルールがはっきりしていて、勝つか負けるか二つに一つで、そこがスポーツの魅力
なのでしょう。プロスポーツの魅力はアスリートの美しさというだけでなく、それが真剣勝負であって、
勝つか負けるか天と地ほどの差が現実にあり、なおかつ厳正なルールにのっとって行われる点にあると
思います。その中で人間がプレーするのでドラマが生まれるのです。
その野球に楽天が参入して、大負けに負けたわけですが、「経営としては黒字なのでOK」
と三木谷社長が言ったとか言わなかったとか。たしかに、そういう面はありますが、黒字でもこのままの弱さじゃ、
成り立たないよな、と思ってしまうのは確かで、なら強ければ赤字でもいいのか、
というとそこのところはプロ野球ファンも球団も親会社もこれまで真剣に考えなかったわけです。
そしてほんとに球団がファンのことを考えて球団経営をしてきたのか、という点でははなはだ疑問でした。
この問題提起は、1リーグ制への動きがかかったときにされたわけですが、ライブドア、楽天やソフトバンクなど
も出てきて球界が再編されることで、深まってきたのではないでしょうか。そんな中、ロッテが31年ぶりに日本一になり、
ファンサービスもいいようで経営もかなりマシになってきた、というのは喜ばしいことです。ファンにとって
よいように経営が変っていけばいいと思うのですが、これからうまく行きますか。
そういえば、先にライブドアがニッポン放送の株を買い付け、フジテレビを狙ってきました。そうかと思えば、
10月には楽天がTBS株を取得し経営統合を申し入れしました。買収の方法も、幕引きの仕方も、
そんな方法もあるのか、とあっと思わせる部分がありました。テレビ局側は、
番組作りのノウハウも持っていないIT企業との経営統合は、視聴者にとっていいことは何もない、
ということで強硬に反対しましたが、じゃ、テレビは視聴者のことを考えた番組作りをほんとに
しているのか、という点ではこころもとないのではないかと思います。プロ野球のほうと
構造はよく似ています。
あれだけ大騒ぎをしながら、結局、何を狙っていたのかよくわからず、ITとメディアの融合、といっても
具体的にどんな新しいサービスが実現するのか、経営統合によって何が違ってくるのか、
その点は不明のまま、ビジョンもなく、おもちゃを欲しがる子供のように欲しがっただけなのではないか、
と思えてきます。
ライブドア・堀江社長の言動が物議をかもし、楽天・三木谷社長が出てきて、なんとなく、こちらのほうが
上手で大人な感じがしたものの、やっぱり違うルールのゲームに参加するときに自分のルールで考えて
押し通そうとするという点ではまったく同じで、
同じヤマ師なら大先輩の孫氏のほうが数段上手であることがはっきりしたようにも思います。
ソフトバンク・ホークスも、まったく物議をかもすことなく自然に受け入れられる形で手にしました。
こと、野球やメディアに関係するところは上手くプレーしているのではないでしょうか。
ま、携帯業界に参入するときは、かなり物議を醸しましたが。
年が明ければ、すぐに仕事、来年度の予算もほぼ確定し、来年度のプロジェクトの計画についての
ヒアリングが始まります。
「これまでできなかったのに、なんで来年度、急にできるようになるのか。」
「いや、これからの私たちは気合が違います。」
「だいたい、この資料を見れば見るほど、去年と同じじゃないか。」
「やらねばならないことは不変だからです。」
「なんで、収入が増えないのに人を増やしてやることも増えるのだ?」
「5年後にはこのテーマで1000億円ほど儲ける予定です。」
「わかった、金はいくら使ってもいいからとにかく成功させろ。」
「予算をさんざん削ってから言わんといてください。」
各研究所所長と、関係する参事(上級)に取り囲まれた中で、このような取締役との禅問答がメインなのですが、
自分のことをたなにあげて攻めてくる某研究所長、2005年度は、予算執行の面で意図して迷惑をかけたので
かなり厳しくあたってくることが想定されます。本気になると、想定の範囲外のことで攻めてくることが多いからなぁ。
幅広く想定して真剣に資料を作るとしよう。
詳しいことはここには書けないのですが、
2006年はまたいろんな面で新しいチャレンジが始まります。
困難にあたることで自分を成長させるチャンスが与えられます。
その分、給料も上がれば言うことないのだけど、こればかりは想定できませんね。
2005年もおしまいです。みなさん、どんな年だったでしょうか。
私は相変わらずサバイバル、オンとオフの切り替えが下手で、
休みも何もなく仕事にいそしんでいる私にとっては、逆に考えれば
毎日が正月気分
と、いえなくもないのではないかと思います。
正月から読もうと思い、4冊ほど本を買っておきました。今年に亡くなったピーター・ドラッカーの
本2冊、
2006年に読む洋書の一冊目、スペンサーシリーズの最新刊"School Days"
そして、2005年に
勉強しようと思い、結局しきれなかった「システム・シンキング入門」です。
読書三昧の正月にしようと思っています。
| 4コママンガ<ハムとラン> とキャラのページ (c)Shimamura,T |
 |
 |
 |
hardy@max.hi-ho.ne.jp |
ええ?みのもんた?
というところが想定範囲外だったので。それで紅白。ちょっとイマイチだったかな。
健康が第一
というのは、やっぱり思うところで、どんなことがあってもへこたれない、意思の力で
やりぬく、といった精神面の強さは体が頑丈でないと発揮できません。
今年は夏から、土曜日曜の朝にテニスの壁打ちに行くことにし、ついに12月末まで続けることができました。
最初は40分くらいでへばっていたのが、スタミナがついてきたのか
60分程度でも少し物足りなく感じるようになってきました。
そして、苦手だったバックハンドも、本を見て少し研究しグリップの角度と足のステップに注意してみると、
あら不思議、少しは上手くなってきました。コントロールもマシになり、
混んでいて1/3面しか使えないときでも、ラリーを続けられるようになってきて、自分としては
かなり満足しています。
朝の早起きの清々しさと、たっぷり汗をかくことの爽快感、心地よい疲労感。ボールを追っているときは、
日ごろの悩みなど余計なことはまったく考えなず、とにかくボールに集中し、体をひたすら動かす、そんな
時間は悪くありません。
通勤の電車の中で寝ているときに、頭で苦手なバックハンドやファーストサービスのイメージを繰り返し
思い浮かべていると、手がヒュッと横に自然に動き、自分で驚いて目を覚ます、といった
不思議な体験もしました。
日ごろのストレスの解消や体力の増強、心と体のバランスをとろう、
というだけでなく、結婚して以来太り気味な体を絞って体重を減らすのも大きな目的でした。
目標は年内に63kgまで減らそうと思ったのですが、残念ながら、64〜65kgまでしか落ちませんでした。
それでも、3kg程度はやせたので、及第点と言えるのではないでしょうか。
最近○×判定が多いので、こんなところは少し自分に甘くして満足しても許しましょう。
来年は62kgを目標にしたいと思います。筋肉がしっかりついて
基礎代謝量が増えればまだ減っていくと思うので、きついダイエットをしなくても、なんとかなるでしょう。
意志の力
が大事だ、というのも、今年意識したことです。ちょうど、意識し得心がいったころ、
意志力革命、という本を読み、強く共感しました。モチベーションというのは確かに大事なのですが、
モチベーションを第一に仕事や物事にあたるとよくないこともあるのです。
モチベーションは移ろいやすく、本質とは関係ない要因で簡単に上がったり下がったりします。だから、
常にモチベーション高く保つように工夫することが大事だ、という人もいるのですが、
そうではなく、モチベーションが低いときでも、やるべきことを実行することが大事なのではないか、
と思うのです。
「お前は好きな仕事しかしないヤツだな」と散々言われてきた私がいまさら、こんなことを言うのも
なんなんですが。
自分が下さなければならない決断が、自分のモチベーションを大きく下げる方向になる可能性
だってたくさんあります。
自分のモチベーションが上がろうが下がろうが関係なく、
時間軸も含めて全体的に広い視野で考え、目標に向かってどうあるべきか考えて決断をし、
すばやく実行に移していくためには、モチベーションをベースに仕事をしていてはうまくいかないこと
も多いのです。
ところで、ここで勘違いしてほしくないことは、「やるべきことをやる」ということと「言われた
ことをやる」は違う、ということです。
「なんで、そんなことやってんだ。」
「だって、やれって言ったじゃないですか。」
これはよく聞く会話なのですが、目的目標を自分で正しく考えた結果の「やるべきこと」
を実行することが大事なのです。
語学
は大事だ、と何べんもこのコラムで書いているのですが、今年は、ちょっと頑張りました。中学のころから
これだけ頑張っていれば、人生違ってたかもしれないと思います。
今年の1月末に中尊寺ゆつ子さんが亡くなり、最後の著作になった「
やっぱり英語をしゃべりたい」を読んでハートに火がつきました。
ディクテーションを中心に、5冊の参考書を最後までやりとげました。今年最後の12月に、年末までに仕上げる
とコミットした「NHKラジオ ビジネス英会話 土曜サロン・ベスト・セレクション」(著:馬越恵美子、発行:(株)DHC、2003年)も、
なんとか30日、31日の追い込みで終了させました。
2004年に洋書を年間3冊読もうと思いつつ3冊目で挫折してそのままだったのですが、その勢いをかって7月に
Robart B ParkerのスペンサーシリーズBad Business"にはじまって、"Project Risk Management Guidlines"、そして
"First, Break All The Rules"の三冊を年末までに読みました。小学生なみの進捗管理をとりいれ、
コミットしたとおりに進めることができました。公にコミットし進捗を見える化することで、自分を追い込むことが
意志の力でやり切るコツの一つです。
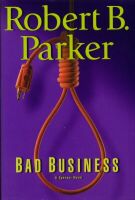 |
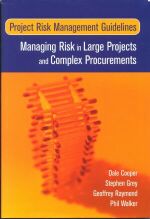 |
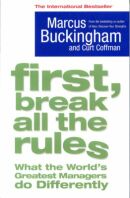 |
この調子なら、来年はかなり読めるはず。2006年は6冊に挑戦します。
今年の反省
といえば、論文を読まなかったことです。2006年は論文を読む時間を
毎日とる、と、ここに宣言します。
もう一つ、ネットに使う時間が長くなったのも問題です。ソーシャル・ネットワーク・サービスの
mixiに手を出したのがちょっとまずく、9月以降、PCの前に座っている時間がかなり長くなっています。
家人にも不評であるうえ、ギターを弾く時間もとれなくなり、自分で制御がうまくできていないところに
フラストレーションを感じます。
2006年は、PCを開く時間を今年後半の半分にしたいと思います。